そんな中で注目したいのが「助けられ力」です。これは、他人の助けを上手に借りて自分の能力を発揮する力。ADHD特性を持つ社会人が、過酷な環境で折れずにやっていくためには、この「助けられ力」が重要なキーワードになります。
1. なぜADHDの社会人に「助けられ力」が必要なのか
ADHDの特性には「不注意」「衝動性」「時間管理が苦手」「忘れっぽい」などがあります。これらはビジネスの現場では“困った特性”とされやすく、結果的に「できない人」と見られてしまうことも。しかし、環境と支援のあり方によっては、むしろ他の人にはない強みを発揮することも可能なのです。
その鍵が「助けられ力」。自分一人でなんとかしようとするよりも、信頼できる人に相談したり、便利なツールに頼ったりすることで、負担を減らし、継続的にパフォーマンスを保つことができます。
2. 実践的な“助けられ力”の身につけ方
①「できないこと」に素直になる
一番大切なのは、「できない自分」を否定しないこと。困りごとを言語化して他者に伝えることで、協力を得る第一歩となります。「〇〇が苦手なんです」と言えることは、決して弱さではなく“工夫する力”の現れです。
②「頼れる人」を見極める
職場にはいろんな人がいますが、「理解しようとしてくれる人」「話を聞いてくれる人」を見つけるのがポイント。人事や産業医、信頼できる先輩など、味方を増やすことで精神的な負担も大きく減ります。
③タスク管理のツールを活用する
スケジュール管理やToDoリスト、リマインダー機能を積極的に活用しましょう。GoogleカレンダーやNotion、アラーム機能など、自分の苦手をカバーしてくれるツールは大きな助けになります。
3. 「助けてもらっていい」ことを知る勇気
多くのADHD当事者は、「迷惑をかけてはいけない」という思いから、助けを求めることに強い抵抗を感じています。しかし、社会とは本来「お互い様」で成り立っているもの。自分も誰かを助け、誰かにも助けてもらいながら成長していくのが自然な形です。
“助けられ力”は、自立できないことの証ではなく、「共に生きる力」。むしろ現代の多様化する職場環境においては、重要なスキルの一つです。
4. 自分の「強み」にも目を向けよう
ADHDの人には、創造性、ひらめき、集中力の高さ(興味のあることに対して)、共感力など、優れた才能も多くあります。困難ばかりに目を向けず、自分の得意を活かす工夫も大切です。
「助けてもらう」ことで自分のリソースを温存し、得意な分野で力を発揮できるようにする。これこそが、ADHD社会人の生き残り戦略です。
5. まとめ|「助けられ力」は生き抜くための知恵
社会に出ると、「一人で頑張ることが美徳」とされがちです。でも、ADHDの特性を持つ人にとって、“誰かに頼ること”は生きるためのスキルです。
自分の困りごとに気づき、それを他者と共有し、サポートを受け入れることで、仕事も人間関係もずっとスムーズになります。そして何より、自分の心が軽くなります。
「助けられ力」は、決して弱さではありません。それは、自分らしく働き、生きていくための力強い知恵なのです。
この記事が、少しでもあなたの心に寄り添うヒントになれば嬉しいです。
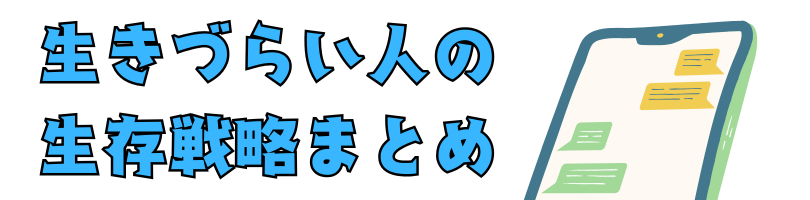
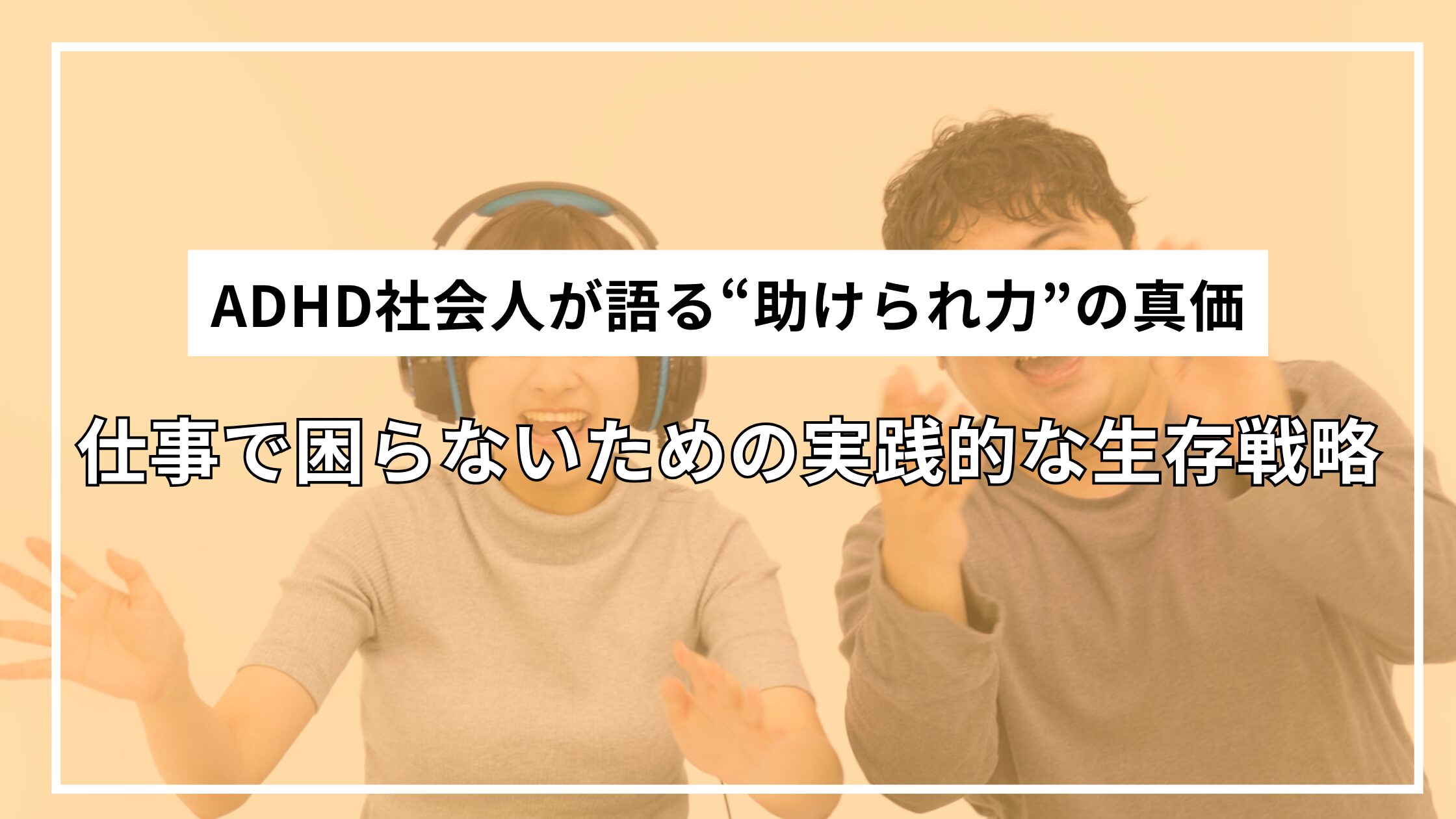

コメント